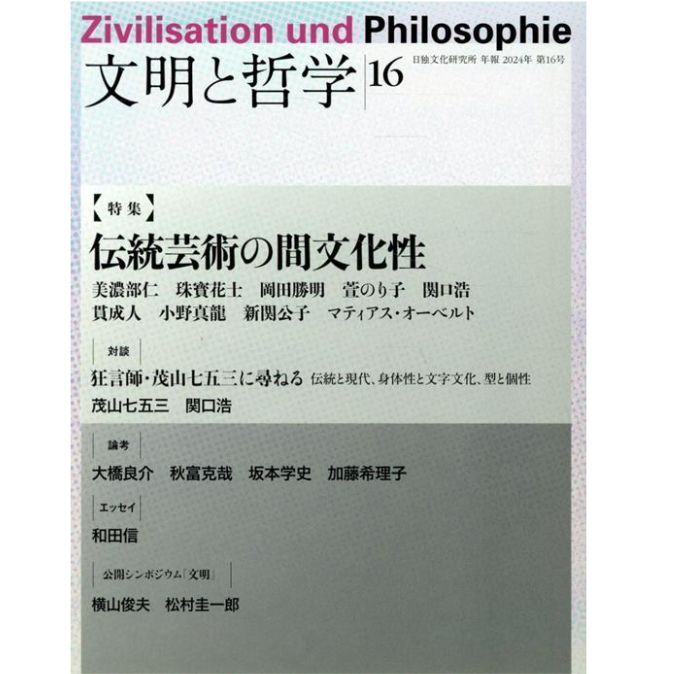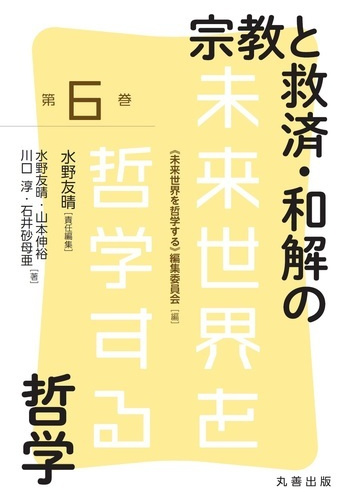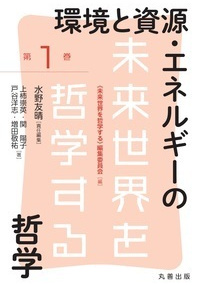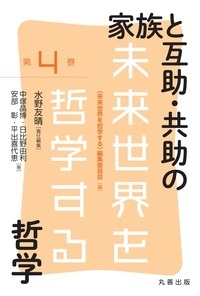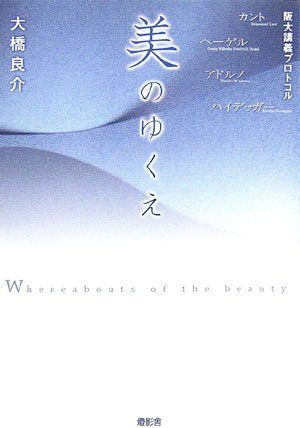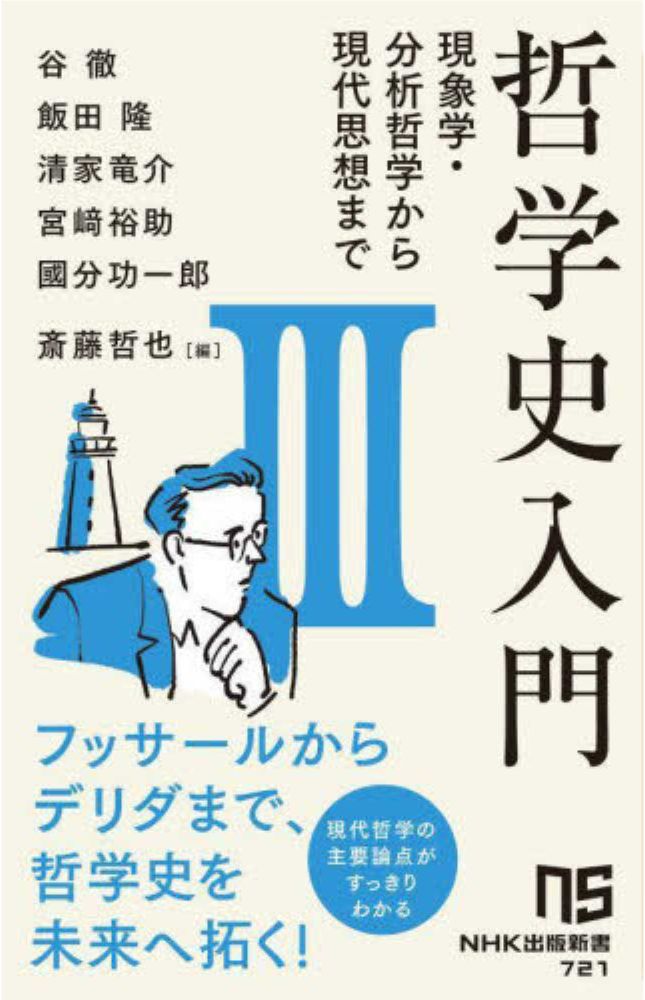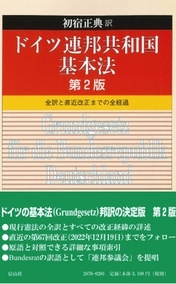What's New (イベント・刊行情報)
哲学講座2025年度初春講座のお知らせ [2025/12/10]
「これからの暮らしと家族、倫理」
 介護、生殖技術、ヤングケアラー、私たちの暮らしに、いま大きな変化の波が及んできています。これから私たちは、どのようなものを支えとし、どのような人と家族となり、どのような倫理のもとで生きてゆくことになるのでしょうか。2025年度初春の哲学講座では『家族と互助・共助の哲学』(『未来世界を哲学する』4、丸善出版、2025年)の責任編者と執筆者をお招きして、これからの暮らしと家族、そして倫理について、みなさまと考えてまいります。みなさまのご参加をお待ちしています。
介護、生殖技術、ヤングケアラー、私たちの暮らしに、いま大きな変化の波が及んできています。これから私たちは、どのようなものを支えとし、どのような人と家族となり、どのような倫理のもとで生きてゆくことになるのでしょうか。2025年度初春の哲学講座では『家族と互助・共助の哲学』(『未来世界を哲学する』4、丸善出版、2025年)の責任編者と執筆者をお招きして、これからの暮らしと家族、そして倫理について、みなさまと考えてまいります。みなさまのご参加をお待ちしています。
※ 本講座は下記の書籍をテキストとするものですが、こちらをお読みでない方もご参加いただけます。
水野友晴(編著)『家族と互助・共助の哲学』(『未来世界を哲学する』4、丸善出版、2025年)
【日程・各回テーマ】
第一講 2026年1月29日(木) 18時00分-19時45分
「講師たちの座談会 これからの暮らしと家族、倫理」
(講師一同、司会:水野友晴)
第二講 2026年2月5日(木)18時00分-19時30分
「家族なき世界における介護の未来 個人の自由と法律・制度」
(中塚晶博)
第三講 2026年2月12日(木)18時00分-19時30分
「ヤングケアラーから考える」
(安部彰)
第四講 2026年2月19日(木)18時00分-19時30分
「生殖と家族の未来とテクノロジー」
(日比野由利)
第五講 2026年2月26日(木) 18時00分-19時30分
「人間の義務としての高齢者介護 尊厳・親切・感謝のコミュニケーション」
(平出喜代恵)
第六講 2026年3月5日(木) 18時00分-19時30分
「質疑応答 みんなで考えるこれからの暮らしと家族、倫理」
(講師一同、司会:水野友晴 )
【講師(自己)紹介】
〇水野友晴
関西大学文学部総合人文学科教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士(文学)。研究テーマは西田幾多郎、鈴木大拙を中心とする日本近代哲学、宗教哲学、比較思想。『家族と互助・共助の哲学』(『未来世界を哲学する』第4巻、丸善出版、2025年)責任編者。
〇中塚晶博
岐阜聖徳学園大学看護学部教授。博士(医学)。神経内科専門医。京都大学大学院医学研究科博士後期課程単位取得退学。研究テーマは神経心理学、フィールド医学、医療人類学、生命倫理。
〇安部彰
三重県立看護大学看護学部教員。立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了。専門は、倫理学・政治哲学、医療・看護倫理学。最近は看護倫理学研究の一環として身体拘束の問題を探求しています。現在は三重に住んでいますが、もとは奈良市の出身で関西をこよなく愛しています。
〇日比野由利
金沢大学融合研究域融合科学系准教授。金沢大学医薬保健研究域医学系を経て現職。博士(保健学)。研究テーマは、社会学、融合科学、生命倫理。
〇平出喜代恵
関西大学文学部総合人文学科准教授。関西大学大学院博士課程後期課程修了。博士(文学)。研究テーマはカントを中心とする西洋近代哲学、倫理学、生命倫理学。とくに、カントが規範的概念として打ち立てた「人間の尊厳」とその現代的意義を考えています。研究内容の硬さと当人のキャラの緩さのギャップをよく指摘されます。
【開催方法】
オンライン ※ 各回、期間限定で受講者向けの記録動画配信あり
【受講料】
一般:12,000円
学生・大学院生・OD:6,000円
※ 賛助会員の方は3割引きにて受講いただけます。
【申込方法】
下記リンクよりお申し込みください
申込用リンク
2025年度公開シンポジウムのお知らせ [2025/11/26]
連続テーマ「世界」第三回
「リアリティとヴァーチャリティ — 現代世界を考える」

日時/2026年1月12日(月・祝) 13時30分~16時30分(13時開場)
会場/ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 大ホール
講演
越前功 (国立情報学研究所教授)
「フェイクニュースの世界~創るAI vs守るAI~」
林喜右衛門 (観世流能楽師)
「能楽作品と謡い方の変化」
コメンテーター:山極壽一(総合地球環境学研究所所長、本研究所名誉顧問)
日独文化研究所 理事・評議員・監事
講師紹介
〇越前功
1997年東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。日立製作所システム開発研究所を経て、現在、国立情報学研究所 情報社会相関研究系 研究主幹・教授。同研究所 シンセティックメディア国際研究センター長。東京大学 大学院情報理工学系研究科 電子情報学専攻 教授。2010年ドイツ・フライブルク大学客員教授、2011年ドイツ・マルティン・ルター大学客員教授。2025年 文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)および電子情報通信学会業績賞、2016年 情報セキュリティ文化賞、2014年 ドコモ・モバイル・サイエンス賞など受賞。IFIP 日本代表。博士(工学)(東京工業大学)。
〇林喜右衛門(林宗一郎)
1979 年京都生まれ。2025年4月5日に十四世林喜右衛門を襲名。謡と仕舞の指南に加え、国内外での公演や、文化財「有斐斎弘道館」を活用した能楽普及活動を展開。2014 年、 平成26年度「京都市芸術文化特別奨励者」の認定。2020年には「重要無形文化財総合認定」を受ける。現代能楽界の第一人者として活躍。
定員:100名/入場無料(要事前申込)
参加申込方法:下記リンクよりお申し込みください
参加申込フォーム
申込締切:2026年1月5日
ワークショッププロシーディング集を刊行しました
2025年7月31日-8月2日に京都北山で開かれたシンポジウム「仏教の〈悲心〉と現代世界」のプロシーディング集が刊行されました。

[目次]
開催趣意と提題(大橋良介) / Konzeption des Workshops und eine These (Ryōsuke Ōhashi) / プログラム / Overcoming The Present-centered View Of Time From Within. From Shuzo Kuki’s Theory of Time To New Presentism (Hiroshi Abe) / Die 17 Nachhaltigkeitsziele in der Buddhistischen Compassion (Dina Barbian) / Keiji Nishitanis Interpretation von Zen-Gedichten (Katsuya Akitomi) / 上田閑照(虚語)と西行(宗教心)、そして親鸞(自然)——「しからしむ言葉(悲心)」における「詩と信(まか)
す心」(岡田勝明) / Inwiefern ist Mono no Aware ein religiöses Gefühl? (Anna Zschauer) / Die Aufgabe der Compassion im Kontext. Einblicke aus Rumänien (Eveline Cioflec) / Von der Interkulturalität zur Natur – eine Phänomenologie der Elemente (Niels Weidtmann) / 〈宗教と女性(性)〉をどう問うか——一燈園創始者・西田天香の書簡から見えてくるもの(末村正代) / 大地・資源・エネルギー、いのち (水野友晴) / 「森」の思想と「受苦者」の連帯——後期E・ユンガーにおける「悲心」の精神(川野正嗣) / 西田幾多郎における自然と慈悲——反自然の場所をもとめて(竹内彩也花) / 近世ヨーロッパ精神と、「自然」概念の問題——西谷啓治『世界観と国家観』、『根源的主体性の哲学』より(加藤千佳) / 「菩薩道」的実践としての哲学——西谷啓治『宗教とは何か』の思索(樽田勇樹)
年報『文明と哲学』第17号を公刊しました
特集:人と人との間——宗教と精神医学
 <目次>
<目次>
巻頭言
大橋良介 ドイツの眼・日本の眼――間文化(インターカルチャー)の時代に
対談
岡村美穂子+水野友晴 鈴木大拙とはどのような人か
論考Ⅰ 特集:人と人との間——宗教と精神医学
森哲郎 『十牛図』に於ける「平常底」
秋富克哉 禅をめぐるハイデッガーと西谷啓治との呼応
清水健信 木村敏と上田閑照――臨床哲学と宗教哲学における西田幾多郎
丸橋裕 ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼカーの場合
村井俊哉 精神科医に「生きる意味」を語ることができるのだろうか?
論考Ⅱ
大橋良介 「世界像」の時代から「真理像」の時代へ――ハイデッガーの「技術」論と仏教の「業」思想
林英哉 障害をめぐる文学の可能性――共生社会の実現に向けて
関口浩 意味ある偶然の一致について――遠藤周作晩年の思索より
加藤希理子 バルト神学におけるキリスト教と社会――その社会主義/共産主義への評価を通して
坂本学史 理想的な法のあり方――堕胎罪と中絶の権利を巡る議論からの一考察
公開シンポジウム「世界」
佐藤勝彦 宇宙のはじまり――進む初期宇宙の観測と残された謎
佐々木閑 仏教の世界観――時間論と因果則
論集『共同研究 共生(続)』を公刊しました
持続可能な世界のための共生の諸層と諸相
 <目次>
<目次>
序論 SDGsの理念と現状
大橋良介 サステイナビリティが意味するもの
髙山佳奈子 持続可能な法秩序の構築
関口浩 サステナビリティについて――ヴェーバー、フロイト、ハイデッガー、脱成長論
第Ⅰ部 現状と次世代への視座
安部浩 地球環境学の構想と予防原則の形而上学的基礎づけ――H・ヨナスの「未来の倫理学」の一解釈
谷 徹 危機と/の意味
谷 徹 つまらない・話――世界の液状化のなかで
高田篤 戦後ドイツ公法学におけるケルゼン――ケルゼンのタブー化と「ケルゼン・ルネッサンス」について
髙山佳奈子 医学研究規制における人と動物の区別
第Ⅱ部 共生の諸層と諸相
和田信 対人援助のあり方とコンパシオーン――震災後傾聴ボランティアに携わる僧侶金田諦應の実践
谷 徹 生・ロゴス・パトス
大橋良介 〈責任〉の深層――人間本性の内なる反―本性について
水野友晴 東洋的思考と創造――鈴木大拙の提言
森哲郎 『十牛図』に於ける「平常底」
加藤希理子 ボンヘッファーの『服従Nachfolge』における受動性――「服従」による抵抗
坂本学史 恥辱という感情と恥辱的な制裁――日本版DBS制度への一試論
村井俊哉 精神科医に「生きる意味」を語ることができるのだろうか?
林英哉 障害をめぐる文学の可能性―共生社会の実現に向けて
秋富克哉 「空と歴史」考――西谷啓治『宗教とは何か』をもとに
シンポジウムプロシーディング集を刊行しました
2023年11月にテュービンゲン大学国際間文化研究センターおよびデュッセルドルフ「恵光」ハウスとの共催で開かれたシンポジウム「仏教とキリスト教の〈自然〉」のプロシーディング集が刊行されました。
 [目次]
[目次]
Exposition des Themas „Die ‚Natur’ im Buddhismus und Christentum“ (Ryosuke Ohashi) / Tübingen 2023 Überlegungen zum religiösen Charakter der Natur inder neueren Umweltbewegung (Eveline Cioflec) / Naturempfindung in der japanischen Ästhetik (Anna Zschauer) / The Concept of “Nature” in Indian Buddhist Scriptures (Shoryu Katsura) / A philosophical merry-go-round− Nature, Self and Self-Nature in Advaita Vedānta (Robert Lehmann) / Natur als ‚Von selbst‘. Anmerkungen zu einer interkulturellenPhänomenologie der Natur (Niels Weidtmann) / Natur und Schöpfung im Mainstream christlichen Denkens und in der christlichen Alleinheitslehre (Johannes Brachtendorf) / “Jinen Nature” in Shinran (Hisao Matsumaru) / Natur bei Zeami:„Von selbst“ als Vollzugsqualität leibgeistiger Praxis (行 gyō) (Leon Krings) / 西谷啓治における自然と空〜『宗教とは何か』における自然を巡る議論〜 (加藤 千佳) / Die „Natur“ beim Dichter Bashô (Katsuya Akitomi) / 鈴木大拙の思想における「自然」 (水野 友晴) / テーマ解題 『仏教とキリスト教の「自然」』 (大橋 良介) / 道元における「自然」 (大橋 良介) / Die Natur beim Zen-Meister Dôgen (Ryosuke Ohashi) / 西田哲学における〈歴史的自然〉 (竹内 彩也花) / Anhang: Die Natur im Schamanismus - Bericht über einen Besuch in einem Dorf im brasilianischen Urwald – (Ryosuke Ohashi)
ワークショッププロシーディング集『無/空の思想の現在と展望』を刊行しました
西田幾多郎生誕150年、西谷啓治生誕120年を記念して2022年に開催された国際ワークショップのプロシーディング集を、文屋秋栄より刊行しました。
 [目次」
[目次」
序言 言葉の半透過性(大橋良介)/Das Problem der Geschichte bei Nishida und Nishitani: vom Aspekt der technischen Welt(秋富克哉)[Abstraktのみ]/“Aesthetics” as a keyhole of interpretation. Looking at the “aestheticians” Nishida and Kuki(Anna ZSCHAUER)/西谷啓治の〈空の立場〉について(加藤千佳)/「日本的」な芸術から世界性への開け — 西田幾多郎と西谷啓治における日本文化論の観点から(長岡徹郎)/Encounter of Art and Philosophy: Nishida Kitarō, Fujioka Sakutarō, and Hishida Shunsō(Michiko YUSA)/Logik der Grenze: Eine Interpretation im Anschluss an Nishida Kitarō(Francesca GRECO)/Eternity as guest: On temporality in Nishida and Nishitani(Enrico FONGARO)/Morphologies of Philosophy: On the Translation of Nishida’s and Nishitani’s Writings into European Languages(Raquel BOUSO)/「絶対者」の論理と「空」の論理 ― ヘーゲルにおける「透明性」と西谷の「即」(大橋良介)/愛のはたらきとしての「辯證法 ― 西谷啓治の初期著作における「近代」と「悪」(ソーヴァ・セルダ Sova P. K. CERDA)/西谷啓治における十字架―近代のキリスト教的系譜(トビアス・バートネック Tobias BARTNECK)/西谷啓治と初期ハイデガーにおける哲学と歴史の問題(樽田勇樹)/The Sangha and the Historicity of History in Nishitani’s Philosophy of Culture(Stephen G. LOFTS)/Neither a person – neither an imperson. Towards the nonduality of Self(Robert LEHMANN)/「もの」自体の現象学 ― 西谷啓治における非主観的な現象学(モルテン・ジェルビーMorten E. Jelby)/Vers une «philosophie de la religion» post-nishitanienne. Réexaminer la philosophie de la religion de Nishitani(杉村靖彦)[Résuméのみ]